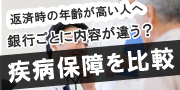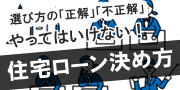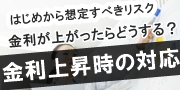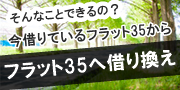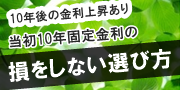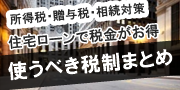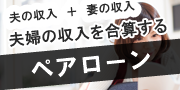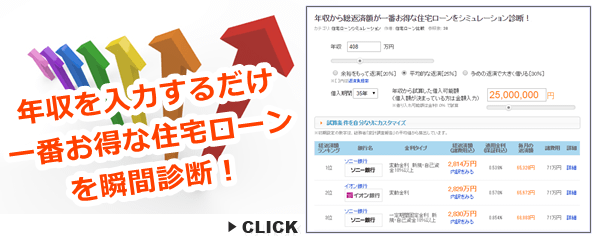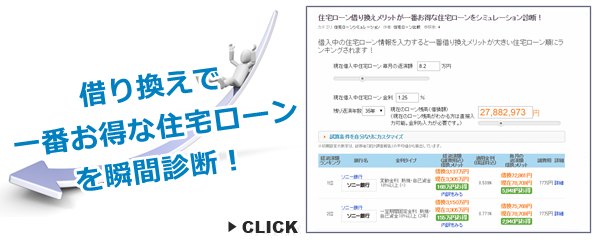元利均等返済と元金均等返済はどちらがお得なのか?徹底比較
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 徹底比較!どっちがお得
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 8446
元利均等返済と元金均等返済はどちらがお得なのか?徹底比較
 住宅ローンを選ぶ際に決めなければならないのは返済方法です。住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があるのですが、どちらがどう違っていて、どちらがお得なのでしょうか?
住宅ローンを選ぶ際に決めなければならないのは返済方法です。住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があるのですが、どちらがどう違っていて、どちらがお得なのでしょうか?
元利均等返済と元金均等返済の意味を比較
元利均等返済
元金と利息を合わせた返済額がずっと同じ返済方法です。借入当初は元金返済分が少なく、利息の返済分が多くなりますが、返済が続くにつれて、元金返済額がおおくなり、利息の返済分が少なくなります。
単純化したイメージでは
- 1ヶ月目の返済額が10万円なら9万円が利息返済、1万円が元金返済
- 30年後の返済額も10万円ですが1万円が利息返済、9万円が元金返済
となります。
元利均等返済のメリット
最初から最後まで返済額が変わらないので返済計画が立てやすい
元利均等返済のデメリット
借入当初の元金返済額が少ない為、総返済額が元金均等返済と比較して多くなる
元金均等返済
元金の返済が一定で、それに利息分の返済が上乗せされる返済方法です。元金は返済期間で割って毎月同じ金額を返済しますが、利息は借入当初の方が大きいので、返済額ははじめの方は高くなり、徐々に返済額が減っていく返済方法です。
単純化したイメージでは
- 1ヶ月目の元金返済は5万円、利息返済が返済額が6万円で返済額は11万円
- 30年後の元金返済は5万円、利息返済が返済額が1万円で返済額は6万円
元金均等返済のメリット
はじめから一定額以上の元金を返済するため総返済額が元利均等返済と比較して少なくなる
元金均等返済のデメリット
毎月返済額が違うので返済計画が立てにくい
元利均等返済と元金均等返済の返済額はどれぐらい違うのか?
3000万円 35年 金利1.5% 金利変動なしと仮定して試算したケース
| 項目 | 元金均等返済 | 元利均等返済 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 借入額 | 3000万円 | 3000万円 | - |
| 金利 | 1.5% | 1.5% | - |
| 初回返済額(合計) | 108,928 | 91,855 | 17,073 |
| 初回返済額(元金) | 71,428 | 54,355 | 17,073 |
| 初回返済額(利息) | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 10年目返済額(合計) | 98,213 | 91,855 | 6,358 |
| 10年目返済額(元金) | 71,428 | 63,146 | 8,282 |
| 10年目返済額(利息) | 26,785 | 28,709 | -1,924 |
| 20年目返済額(合計) | 87,500 | 91,855 | -4,355 |
| 20年目返済額(元金) | 71,428 | 73,359 | -1,931 |
| 20年目返済額(利息) | 16,071 | 18,496 | -2,425 |
| 30年目返済額(合計) | 76,786 | 91,855 | -15,069 |
| 30年目返済額(元金) | 71,428 | 85,222 | -13,794 |
| 30年目返済額(利息) | 5,357 | 6,633 | -1,276 |
| 利息合計 | 7,893,570 | 8,579,013 | -685,443 |
| 総返済額 | 37,893,570 | 38,579,013 | -685,443 |
となります。
見ておわかりの通りで、元利均等返済は元金の支払いが一定です。徐々に利息の返済分が減っているのですが、元金均等返済の方は返済額が一定ですが、その内訳が毎回違うことがわかります。
とくに注目しなければならないのは「約68万円も、元金均等返済の方が高くなってしまう」ということです。
住宅ローンの金利というのは複利計算で計算されていくものなので、できるだけ早い段階で元金を減らしていける「元金均等返済」の方が、最終的な総返済額は安くなるということなのです。
さらに金利が10年後に1.0%上昇したケースを試算してみます。
| 項目 | 元金均等返済 | 元利均等返済 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 借入額 | 3000万円 | 3000万円 | - |
| 金利 | 1.50% | 1.50% | - |
| 金利変動 | 10年後に1.0% | 10年後に1.0% | - |
| 初回返済額(合計) | 108,928 | 91,855 | 17,073 |
| 初回返済額(元金) | 71,428 | 54,355 | 17,073 |
| 初回返済額(利息) | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 10年目返済額(合計) | 116,071 | 103,035 | 13,036 |
| 10年目返済額(元金) | 71,428 | 55,187 | 16,241 |
| 10年目返済額(利息) | 44,643 | 47,848 | -3,205 |
| 20年目返済額(合計) | 98,214 | 103,035 | -4,821 |
| 20年目返済額(元金) | 71,429 | 70,844 | 585 |
| 20年目返済額(利息) | 26,785 | 32,192 | -5,407 |
| 30年目返済額(合計) | 80,357 | 103,035 | -22,678 |
| 30年目返済額(元金) | 71,429 | 90,940 | -19,511 |
| 30年目返済額(利息) | 8,928 | 12,095 | -3,167 |
| 利息合計 | 10,581,086 | 11,933,237 | -1,352,151 |
| 総返済額 | 40,581,086 | 41,933,237 | -1,352,151 |
となります。
金利変動なしのときの総返済額の差が約68万円だったのに対して、金利が1.0%上昇しただけで、総返済額の差は135万円まで広がっているのです。
元金を早めに返しておける「元金均等返済」の方が、金利上昇時には有利に働くということなのです。
元利均等返済と元金均等返済はどちらがお得なのか?の考察
一般的には返済額が固定されているため、返済計画を立てやすいとして、銀行にすすめられがちな「元利均等返済」ですが、総返済額で見ると大きな損をしていることになるのです。
はじめの方の元金返済が少ない分、利息が膨らんでしまうのです。
なぜ、銀行は「元利均等返済」をすすめてくるのか?というと利息=銀行の取り分が大きくなるからなのです。
編集部の意見としては、金利が上がれば返済額など変動してしまうので、返済計画が立てやすいというメリットは重要なものではないと考えます。
金利が超低金利時代の今は、今後の金利上昇は多かれ少なかれ、あると予測されます。だからこそ、金利上昇リスクに対応するためには早めに元金の返済を進めておくべきなのです。
住宅ローンの返済方法を比較するときには、「元金均等返済」を選ぶべきなのです。
「元利均等返済」をすすめてくる銀行は、自分の利益を増やしたいだけなのです。
騙されないようにメリットデメリットを正確に把握する必要があるのです。