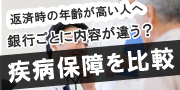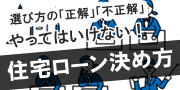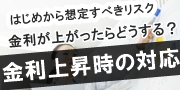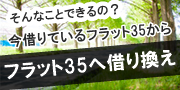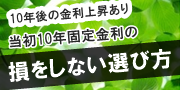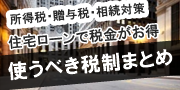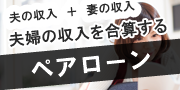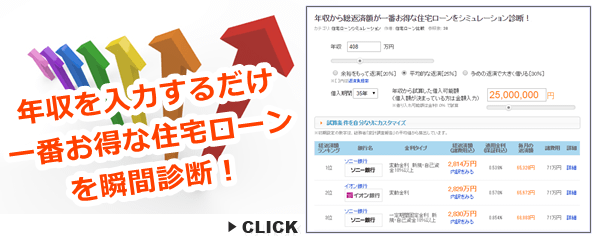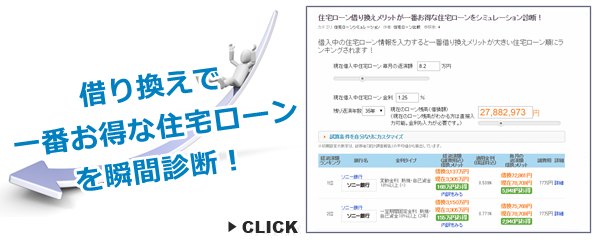住宅ローンの5大リスク
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: はじめての住宅ローン
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 51720
住宅ローンの5大リスク
 住宅ローンというのはあくまでも「借金」なのです。住宅ローンを借りる際には、抑えておかなければならないのは「リスク」です。今回は、住宅ローンのリスクの中でも重要なものをピックアップして解説しました。
住宅ローンというのはあくまでも「借金」なのです。住宅ローンを借りる際には、抑えておかなければならないのは「リスク」です。今回は、住宅ローンのリスクの中でも重要なものをピックアップして解説しました。
金利上昇リスク
住宅ローンの金利は2010年以降は、過去に例を見ない「超低金利」時代です。また、ネット銀行の台頭もあって、人気があるのは「変動金利」「当初固定金利」となっています。
注意しなければならないのは「変動金利」「当初固定金利」は金利上昇リスクを伴うということです。
借入額が3000万円の場合、金利が1.0%上昇すると総返済額は600万円以上高くなるのです。
変動金利が現在0.5%で「これは安い。」となっていても、1.5%になれば+600万円、2.5%になれば+1200万円も総返済額が上がってしまうのです。
「そんなに金利は上がらないでしょ?」
と思う方も多いかもしれませんが、1990年代後半のバブル時代には金利は5%~6%という時代もあったのです。同じまでに行く可能性は低いものの、半分の2.0%~3.0%ぐらいは全然ありうる金利水準なのです。
「変動金利」「当初固定金利」を選ぶ場合には、金利上昇リスクについても、慎重に検討する必要があります。
返済不能リスク
日本では終身雇用という文化がほとんど機能しなくなっています。今後、さらに欧米型のビジネススタイルが定着すれば、「利益を上げられない人材は解雇される。」ということも現実的になってきます。
超高齢化社会が進み、給料もなかなか上がらない状況では、社会保障費や税金ばかり上昇してしまって、住宅ローン返済に回せる原資がなくなってしまう可能性も高いのです。
返済できなくなると、最悪なのは「住宅ローンが払えずに泣く泣く住宅を売却したけど、それでもローン残債を完済できず、借金だけが残ってしまう。」という状況です。
こうならないためには、余裕を持った物件選びをしなければなりません。
銀行は、マイナス金利の影響もあり、担保がある住宅ローンの融資額を増やしたい意向があるため、かなり返済が厳しいと思われる属性の方にも、ガンガン貸してしまっている印象です。高額な借り入れをしすぎると、返済不能になるリスクがあるので注意しなければなりません。
不動産価格の下落リスク
不動産価格は2020年のオリンピックまで上昇しています。この理由は、安倍政権が導入したマイナス金利の影響により、融資金利が下がり、不動産需要が増えたからです。しかし、冷静に考えてみれば、どう考えても人口が減る中で物件は立ちすぎています。空き家問題も経済化している中で、オリンピックが終われば不動産バブルは崩れ、大幅に不動産価格が下落することは目に見えているのです。
不動産価格が下落すると、住宅ローン残債は高い状態なのに、マイホームを売却しても、購入時よりも全然安くなってしまい、買い替えをしたくても、ローン残債を賄えずに借金が残ってしまう可能性も出てきてしまうのです。この場合には、借り換えをしたくても、借り換え先の銀行の審査も通りにくくなってしまいます。
物件購入を検討する際には、不動産価格の下落リスクについても、頭に入れておく必要があるのです。
離婚リスク
日本でも、3組に1組は離婚をしている現状です。離婚は他人ごとではないのです。
住宅ローンの契約を旦那さんだけが行っていた場合でも、離婚によって財産分与で住宅を手放さなければならないケースもあります。
最悪なのは「夫婦の収入合算」「夫婦のペアローン」を利用して住宅ローンを組んでいた場合です。「収入合算」であれば、妻は夫の住宅ローンの連帯保証人になっているため、離婚後も、連帯保証人は継続しなければなりません。「ペアローン」の場合でも、住んでいる物件は一つなのに持分が夫婦で決まってくるため、どちらかがどちらかの持分を買い取るしかなくなってしまいます。買い取れるお金があれば、はじめから住宅ローンを組まないので、結局マイホームを手放す選択をする方も少なくないのです。
離婚リスクは、住宅ローンの中でも、現実的かつ、影響が大きいリスクとして認識する必要があります。
転勤リスク
転勤をする場合に自宅をどうするのか?が大きなリスクとなります。
現在であれば、不動産価格は上昇している最中ですので、転勤が決まったとしても
- 単身赴任すれば良い
- 転貸で誰かに貸せば良い
- 売却すれば良い
という選択肢がありますが
人口減少により不動産価格が大きく低下する、物件の供給過多が表面化した場合には
- 転貸しても借り手がいない
- 売却するにしても、購入価格とはかけ離れた安い金額でしか売れない
という問題がでてきてしまいます。
転勤が多いことが予測されている職業の方ほど、不動産価格の下落リスクも含めて、慎重に物件を選ばなければならないのです。