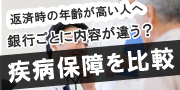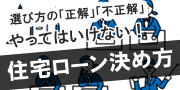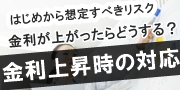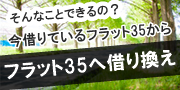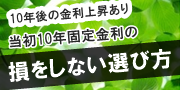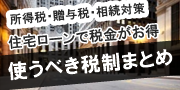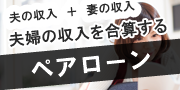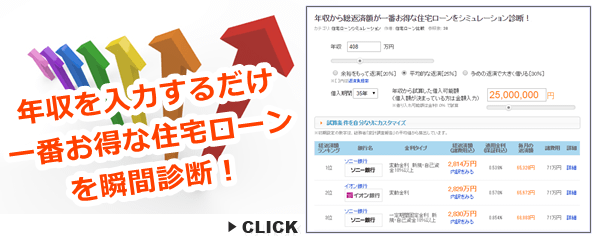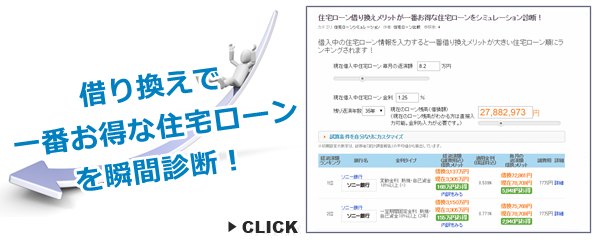住宅ローン減税条件の落とし穴
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 21771
住宅ローン減税の適用条件には知られていない落とし穴
 住宅ローン減税の制度適用にはあまり知られていない適用条件があります。気をつけておかないとこれらの適用条件をクリアできずに、予定していた減税による控除が受けられなくなる可能性があります。
住宅ローン減税の制度適用にはあまり知られていない適用条件があります。気をつけておかないとこれらの適用条件をクリアできずに、予定していた減税による控除が受けられなくなる可能性があります。
住宅ローン減税の落とし穴を把握しておこう
[平成○年○月○日現在法令等]
住宅ローン減税とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成○年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
注意事項
・所得税からの控除であること
・マイホーム(居住用)の住宅購入、増改築であること
※投資用物件には適用できない
住宅ローンの適用条件での落とし穴
居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅ローン減税の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
①新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
→取得から半年いないに居住し、その年末まで引き続き居住している場合
注意事項
※贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。
※投資用物件や別荘など、常時住む居住用以外の住宅では適用されません。
②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
→退職金など一時的に多額の収入があり、その年1年間の合計所得(≠年収)が3000万円を越えてしまうと、その年はローン控除が受けられなくなります。
注意事項
※当たり前ですが、3000万円以上所得があるならローン組む必要もない余裕のある人という判断でしょう。
③新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
→50平米以上、半分以上が自己居住用という条件。
注意事項
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
・実は、床面積の計算方法は2種類あり、これを誤ると50平米で借りたつもりが、政府の計算方法では49平米しかないということも起こります。
「パンフレットの面積(壁芯面積)」
マンションなどの耐火建造物はコンクリートで覆われていて、そのコンクリートには約10~15cmの厚みがありますが、床面積を計算する時に、コンクリートの厚みの「中心線」を基準に測定した面積のことです。部屋の角(かど)に柱が出っぱっていても、床面積に含まれます。
「登記簿の面積(内法面積)」
コンクリートの厚みの中心線ではなく、壁の内側(室内側)を基準に測定した面積です。実際に使用可能な面積となります。
そして重要なことは、住宅ローン控除の基準になる床面積は後者の登記簿の面積となります。つまり、パンフレットの面積が50平方メートル以上でも、登記簿面積が50平方メートル以上あるとは限らず、そのため、せっかくの住宅ローン控除が受けられなくなるケースがあり得るのです。
登記簿の面積が確定するのが実際に建物が完成した後なので、契約時には正確な登記簿面積はわかりません。そこで、パンフレットの面積が50平方メートルちょっとという場合は、可能であればもうひと回り広い間取りにすることをおすすめします。
④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
※勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
→10年以上の住宅ローンを組んでいること。
注意事項
・「勤務先」から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けていると見なされるため、控除対象から外されてしまう点です。
・銀行や住宅金融支援機構など、民間や政府系機関からの融資であれば、たとえ金利が1%未満でも住宅ローン減税の対象外にはなりません。
⑤居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
→もうわけがわかりませんね。購入年とその前後2年の計5年間の間に「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないことという意味です。
以上、落とし穴をちゃんと回避した物件購入をしないと、住宅ローン減税をうけることができなくなります。注意しましょう。