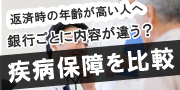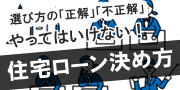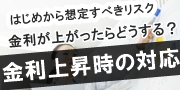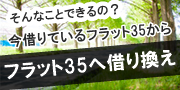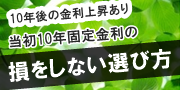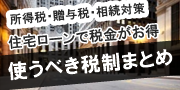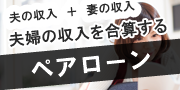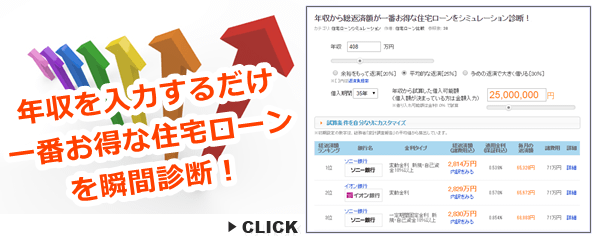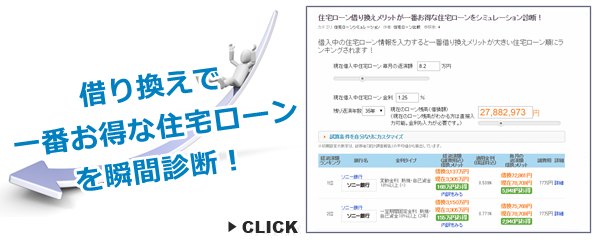住宅ローン・住宅購入がお得になる税制(減税)まとめ/2016年最新
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 10259
住宅ローン・住宅購入がお得になる税制(減税)まとめ/2016年最新
住宅ローンを利用してマイホームを購入するときには、政府が景気回復の一環としてさまざまな減税制度を用意しています。これは住宅ローン減税(住宅ローン控除)だけではありません。ここでは、今利用できる住宅ローン・住宅購入がお得になる税制(減税)をまとめて紹介しています。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
利用できる期間
平成31年6月まで
住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは
10年以上の住宅ローンを利用して、マイホームを購入する方に毎年の年末時点の住宅ローン残高の1.0%を所得税や住民税から控除できる減税制度のことで、10年間控除が可能です。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の制度概要
新築
| 項目 | 一般(新築・中古住宅) | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
|---|---|---|
| 控除対象の借入金額 | 次の条件を満たす10年以上の住宅ローンの年末残高 1.住宅の新築、取得(中古住宅も含む) 2.住宅の取得とともにする敷地の取得 3.一定の増改築(リフォーム) | 次の条件を満たす10年以上の住宅ローンの年末残高 1.住宅(認定住宅)の新築、取得 2.住宅(認定住宅)の取得とともにする敷地の取得 |
| 適用条件 | 1.居住用の住宅であること 2.10年以上の住宅ローンを組むこと 3.床面積50㎡以上 4.中古住宅の取得の場合 築年数20年以内又は耐震基準に適合すること | 1.認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)であること 2.居住用の住宅であること 3.10年以上の住宅ローンを組むこと 4.床面積50㎡以上 |
| 控除額(減税額) | 住宅ローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大4000万円 各年の控除限度額:40万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大2000万円 各年の控除限度額:20万円 | 住宅ローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大5000万円 各年の控除限度額:50万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大3000万円 各年の控除限度額:30万円 |
| 控除期間 | 10年間 | 10年間 |
| 控除の適用期限 | 平成31年6月 | 平成31年6月 |
| 所得要件 | 年収3,000万円以下 | 年収3,000万円以下 |
リフォーム
| 項目 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
|---|---|---|
| 控除対象の借入金額 | バリアフリー改修工事を含む5年以上のリフォームローン | 省エネ改修工事を含む5年以上のリフォームローン |
| 適用条件 | 1.居住用の住宅であること 2.バリアフリー改修工事を含むリフォームであること 3.床面積50㎡以上の住宅のリフォームであること | 1.居住用の住宅であること 2.省エネ工事を含むリフォームであること 3.床面積50㎡以上の住宅のリフォームであること |
| 控除額(減税額) | リフォームローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12.5万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12万円 | リフォームローンの年末残高 × 控除率 = 毎年の控除額(減税額) 平成26年4月~31年6月 控除率:1.0% 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12.5万円 ※消費税の税率が8%、10%以外の場合 控除対象ローン年末残高:最大1000万円 各年の控除限度額:12万円 |
| 控除期間 | 5年間 | 5年間 |
| 控除の適用期限 | 平成31年6月 | 平成31年6月 |
| 所得要件 | 年収3,000万円以下 | 年収3,000万円以下 |
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の考察と注意点
住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、毎年の年末のローン残高の1.0%が10年間減税になる制度です。年末残高で4000万円ローンが残っていれば、40万円も所得税や住民税が減税になります。これが10年続くのですから、数百万円単位でのお得になる制度であり、使わない手はありません。
注意しなければならないのは、住宅ローン減税(住宅ローン控除)を使おうとしたのに、その条件を理解しておらず購入後に、その物件では利用できないことが発覚してしまうことです。
- 住宅ローンは10年以上の返済期間がなければならないこと
- あくまでも自分が住むマイホームでなければならないこと
- 床面積50㎡以上というのは登記上の面積であり、内法面積。パンフレットの面積と違うこと
などに注意が必要です。
すまい給付金
利用できる期間
平成31年6月まで
すまい給付金とは
住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、所得税や住民税が減税できる制度です。所得税や住民税は収入に応じて変動するため、低所得者は所得税や住民税が元々少ないのです。そのため、住宅ローン減税(住宅ローン控除)の減税分を使いきれないことも多く、景気刺激策としては低所得者に効果が出にくいものとなってしまっているのです。
それをカバーするために作られた「すまい給付金」は住宅購入者に対して、年収に応じて現金を給付する制度です。年齢制限はあるものの、現金購入者も給付が受けられます。
すまい給付金の制度概要
| 給付条件 | 住宅ローン利用 | 現金購入 |
|---|---|---|
| 対象者の条件 | 1.不動産登記上の住宅所有者 2.住民票で居住が確認できる方 3.収入が一定の基準以下 消費税 8% → 510万円以下が目安 消費税10% → 775万円以下が目安 | 1.不動産登記上の住宅所有者 2.住民票で居住が確認できる方 3.収入が一定の基準以下 消費税 8% → 510万円以下が目安 消費税10% → 775万円以下が目安 4.年齢が50歳以上 消費税10% → 650万円以下の要件追加 |
| 対象住宅の条件 | 1.床面積が50㎡以上 2.第三者機関の検査 新築住宅 → 施行中の第三者の検査 中古住宅 → 売買時の第三者の検査 | 1.床面積が50㎡以上 2.第三者機関の検査 新築住宅 → 施行中の第三者の検査 中古住宅 → 売買時の第三者の検査 3.一定の性能の確保 新築住宅 → フラット35Sの基準を満たす住宅 中古住宅 → 現行の耐震基準を満たす住宅 |
| 給付額 | 給付額 = 給付基礎額 × 持ち分割合 ※給付基礎額算出の収入は都道府県民税の所得割額 【消費税 8%の場合】 所得割額:6.89万円以下(年収425万円以下) 30万円 所得割額:8.39万円以下(年収475万円以下) 20万円 所得割額:9.38万円以下(年収510万円以下) 10万円 【消費税 10%の場合】 所得割額: 7.60万円以下(年収450万円以下) 50万円 所得割額: 9.79万円以下(年収525万円以下) 40万円 所得割額:11.90万円以下(年収600万円以下) 30万円 所得割額:14.06万円以下(年収675万円以下) 20万円 所得割額:17.26万円以下(年収775万円以下) 10万円 ※上記の年収は目安。あくまでも所得割額で判断 | 給付額 = 給付基礎額 × 持ち分割合 ※給付基礎額算出の収入は都道府県民税の所得割額 【消費税 8%の場合】 所得割額:6.89万円以下(年収425万円以下) 30万円 所得割額:8.39万円以下(年収475万円以下) 20万円 所得割額:9.38万円以下(年収510万円以下) 10万円 【消費税 10%の場合】 所得割額: 7.60万円以下(年収450万円以下) 50万円 所得割額: 9.79万円以下(年収525万円以下) 40万円 所得割額:11.90万円以下(年収600万円以下) 30万円 所得割額:14.06万円以下(年収675万円以下) 20万円 所得割額:17.26万円以下(年収775万円以下) 10万円 ※上記の年収は目安。あくまでも所得割額で判断 |
| 適用期限 | 平成31年6月までに引き渡し、入居が完了した物件 | 平成31年6月までに引き渡し、入居が完了した物件 |
すまい給付金の考察と注意点
すまい給付金も、住宅ローン減税(住宅ローン控除)と同じく、利用しなければただ損をするだけの制度です。利用しない手はありません。ほとんど住宅ローン減税(住宅ローン控除)と同じ適用条件ですので、住宅ローン減税(住宅ローン控除)が受けられるのであれば、すまい給付金も受けられることになります。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)が適用外の現金一括購入者も、年齢が50歳以上であれば利用できるので申請を忘れないようにしましょう。
住宅取得等資金の非課税制度
利用できる期間
平成31年6月まで
住宅取得等資金の非課税制度とは
住宅購入資金を、父母、祖父母から贈与してもらった場合に贈与税が一定の金額までは非課税となる制度です。将来受け取る財産を非課税で贈与できるので、生前贈与などの相続対策として利用されています。
住宅取得等資金の非課税制度の制度概要
限度額
| 住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 住宅を消費税10%で取得 | 住宅を消費税10%以外で取得 | ||
|---|---|---|---|---|
| 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | |
| 平成28年1月~平成28年9月 | - | - | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
| 平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
適用要件
| 相続時精算課税制度 | 住宅取得等資金の非課税制度 |
|---|---|
| 非課税枠 | 300万円~3000万円 ※別表参考 |
| 併用 | 相続時精算課税制度と併用可能。 |
| 贈与者 | 直系尊属(受贈者の父・母・祖父・祖母等) ※年齢制限なし |
| 受贈者 | 贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属 日本国内に住所を有する人 合計所得額が2,000万円以下 |
| 税率 | 「非課税枠+基礎控除額」を超える部分に対して累進課税(10%~55%) |
| 贈与財産 | 自己の住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること |
| 適用期間 | 平成27年1月1日から平成31年6月30日の贈与 |
| 物件の要件 | ・床面積(登記簿面積)50㎡以上 240㎡以下 ・店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅 |
| 中古住宅購入時の追加要件 | ・耐火建築:家屋の取得の日以前25年以内に建築 ・耐火建築以外:家屋の取得の日以前20年以内に建築 ・一「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結証明」 ・耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合 |
| リフォーム時の要件の追加要件 | ・工事費用が100万円以上であること ・居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。 ・「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明された工事であること |
| 手続き | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用に関する書類を納税地の所轄税務署に提出 |
住宅取得等資金の非課税制度の考察と注意点
住宅取得等資金の非課税制度は、贈与を受けなければ父母が亡くなったときに相続財産として相続することになり、基礎控除額(3000万円+相続人×600万円)を超える分に相続税が発生します。非課税で生前贈与すれば、相続財産が減り、相続税も減るということになります。
住宅取得等資金の非課税制度を利用すべきかどうか?のポイントは「父母や祖父母に基礎控除額(3000万円+相続人×600万円)を超える財産があるか?」「贈与できる預貯金や現金化可能な財産があるかどうか?」の2点と言っていいでしょう。
基礎控除額(3000万円+相続人×600万円)を超える財産がなければ、将来受け取っても相続税はかかりませんので、生前贈与を受けるメリットと言うのは住宅ローンの利用額が減ることでの利息軽減ぐらいしかありません。しかし、基礎控除額(3000万円+相続人×600万円)を超える財産というのは、現金だけでなく、預貯金、有価証券、不動産、動産・・・とすべての財産が当てはまるので、東京都内に土地を持っているだけでも簡単に超えてしまうものなのです。
住宅購入時には両親や祖父母とも相談の上、財産が基礎控除額以上になるようでしたら、相続税もシミュレーションしてみて「住宅取得等資金の非課税制度」を利用することをおすすめします。