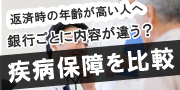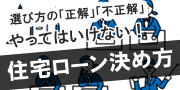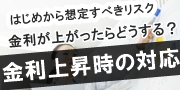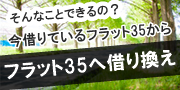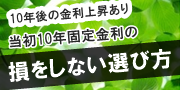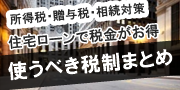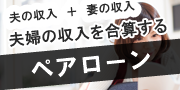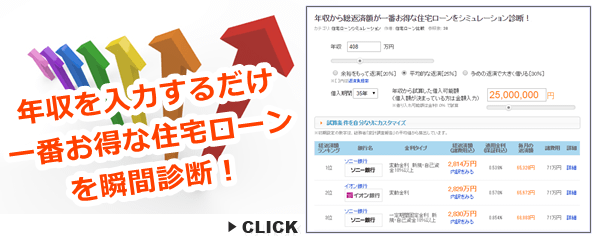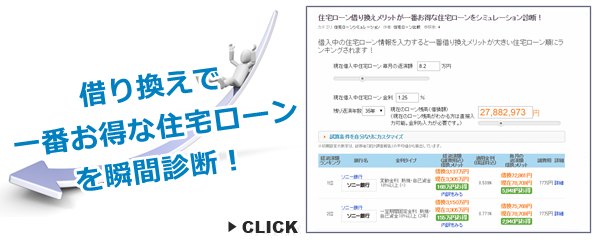住宅ローンの諸費用の見方
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンの種類やサービス
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 239870
住宅ローンの諸費用の見方
住宅ローンには、様々な諸経費が必要になってきます。事務手数料、保証料、団体信用生命保険特約料、繰り上げ返済手数料、金利タイプ変更手数料、印紙税、登記関係の費用、火災保険料、上げていけばキリがありません。ただし、この諸費用、軽く見ているとバカにならない金額にすぐに百万単位で差が出てきます。住宅ローンの諸費用の項目と考え方をチェックしましょう。
1.金額の大きい2大諸費用「保証料」「事務手数料」
金額の大きい諸費用として事務取扱手数料(事務手数料)と保証料の2つが挙げられます。
保証料とは
住宅ローンを提供している銀行が、保証会社に保証をつけるために必要な費用であり、融資する際の前提条件として扱われている銀行も少なくない。これは、万が一借りた人がローンを支払えない状況になった際に、保証会社にローンを肩代わりしてもらうために必要な保証のことである。 一般的に一括で払う「外枠方式」と金利に上乗せして払う「内枠方式」があり、借入額の0.2%というのが相場ではあるが、実は銀行によって結構マチマチなので、住宅ローンを比較検討する際には必ず考慮にいれる必要がある
事務手数料とは
住宅ローンの貸付にかかわる手数料のこと。一般的に大手都市銀行(メガバンク)は事務手数料が31,500円のところが多く、ネット銀行は借入額の2.1%を採用しているところが多い。つまり、保証料と事務手数料は銀行ごとに違い、傾向として大手都市銀行(メガバンク)や地銀などは事務手数料を数万円に安い代わりに保証料を高く設定し、借入額の2.1%という金額がかかり、ネット銀行は保証料を無料にする代わりに事務手数料を借入額の0.2%に設定し、お互いほぼ同じ費用が住宅ローンの際には、利用者から支払われる仕組みになっている。これは、保証料は途中で住宅ローンの借り換えを行った際に戻ってくるお金である(借り換え先で必要)のに対し、事務手数料は借り換えをした際には変換されない。銀行側の視点にたってみると、同じ手数料に見えても、保証料でもらうよりも、事務手数料でもらった方が、儲かるのである。だからこそ、そのことに気づいたネット銀行は、住宅ローンの手数料を保証料から事務手数料に移したのである。
しかし、今や住宅ローンも低金利競争、サービス競争の時代になり、事務手数料も保証料も金利も低い銀行が出てきている。住宅ローンの検討の際に、この諸経費を考慮にいれなければ、数百万の損をすることも起こりうるのである。
2.各銀行の「保証料」「事務手数料」一覧
| 銀行名 | 保証料 | 事務取扱手数料 |
| SBI新生銀行 SBI新生銀行パワースマート住宅ローン | 0円 | 55,000円(税込)/安心パック(介護保障・コントロール返済)110,000円(税込)/安心パックW(家事代行・病児保育)165,000円(税込) ※変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>は、事務手数料 借入額の2.20% |
| 住信SBIネット銀行 住宅ローンWEB申込コース | 0円 | ご融資金額の2.20% |
| ソニー銀行 住宅ローン金利プラン | 0円 | 44,000円 |
| ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン金利プラン | 0円 | ご融資金額の2.20% |
| イオン銀行 イオン銀行住宅ローン 手数料定率型 | 0円 | ご融資金額の2.20% |
| イオン銀行 イオン銀行住宅ローン 手数料定額型 | 0円 | 110,000円 |
| 三井住友住宅銀行 三井住友住宅ローン | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,600円~2,473,110円 <元金均等返済> 489,870円~1,961,100円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ | 33,000円 |
| みずほ銀行 みずほ住宅ローン みずほ借り換え住宅ローン | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,330円~2,164,410円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ | 33,000円 |
| 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行住宅ローン | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間30年、の場合 <一括前払い型> 574,110円~2,296,440円 <利息組込み型> 0円~1,722,330円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ | 33,000円 |
| 楽天銀行 フラット35 | 0円 | ご融資金額の1.43%(楽天銀行口座指定で1.10%) |
| 東京スター銀行 スターワン住宅ローン | メンテナンスパック0.300%~0.702% | 110,000円 |
| 東京スター銀行 スター住宅ローン | 無料 | 借入額の2.0%(税別) |
| りそな銀行 りそな住宅ローン | 【外枠方式】借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 元利均等返済>618,420円 ※借入金額・借入期間により変動。一部商品により異なる。また、措置期間がある場合には、金額が異なる場合がある。 【内枠方式】金利0.2%上乗せ | 33,000円 |
| 三井住友住宅信託銀行 三井住友信託銀行の住宅ローン | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,330円 <元金均等返済> 490,980円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ | 33,000円 |
見てお分かりの通りに、
ネット銀行系は、保証料が0円で事務手数料が借入額の2.1%というところが多い。これは3000万円の借入の場合に63万円の費用がかかる計算になる。しかし、ソニー銀行やSBI新生銀行など、事務手数料を借入額に対しての割合ではなく、一律で5万円、4万2千円という63万の1割以下の低価格にしている銀行もある
大手都市銀行、メガバンク系は、事務手数料はほとんど31500円で、保証料は非常に幅を設けている銀行が多い。三井住友銀行であれば、一括支払いの場合3000万円の借入で618,600円~2,473,110円と非常に幅のある料金設定になっている。これは、保証会社の審査によって決定される。信頼できる人であれば最低ラインの61万で保証料は大丈夫だが、そうでない人は247万という大きな金額になってしまう可能性が高い。
つまり、諸費用だけを見てみるとネット銀行のSBI新生銀行とソニー銀行が抜群に安いといういことがわかるだろう。三井住友銀行で焼く250万になる可能性もあれば、SBI新生銀行で5万円で済む可能性もある。単純に250万も諸経費だけで差が出てしまうのである。住宅ローンの選択には諸経費も比較検討しなければ大きな損をしてしまう可能性があるだろう。
3.フラット35だけに必要な団体信用生命保険特約料
もうひとつ、チェックしなければならない諸経費があります。それは、団信と呼ばれる、借りた方が死亡して返済が不能になったときに住宅ローンの返済の残債がなくなるという生命保険です。一般的な銀行は、この団信の加入を住宅ローン貸付の条件にしているため、必ず入る必要があり、かつこの団体信用生命保険特約料は無料で銀行側が負担してくれるようになっている。ただ、国の独立行政法人である住宅金融支援機構が提供するフラット35は、この団信の加入条件がなく、団信に入る場合は費用がかかる。じゃあ、入らなければいいという方もいるかと思いますが、団信に加入しない場合は、死亡した場合の住宅ローンの債務は遺族が相続することなり、大きな負担をかけることになるため入るべき保険と考えたほうがいいだろう。
団信特約料目安
| 返済期間 | 借入額 | 金利 | 特約料総支払額 |
| 35年 | 3000万円 | 1.85% | 2,119,300 |
| 30年 | 3000万円 | 1.85% | 1,793,400 |
| 25年 | 3000万円 | 1.85% | 1,475,100 |
| 20年 | 3000万円 | 1.57% | 1,156,300 |
| 15年 | 3000万円 | 1.57% | 858,600 |
35年の3000万を借り入れると200万を超えてくる負担になってくる。他の銀行では、これが0円なのだ。さらにフラット35も扱う銀行側の事務手数料は必要なため、2重で諸経費がかかるので注意が必要。ちなみに保証料は0円である。
4.繰上げ返済手数料と金利タイプ変更手数料
大きな金額ではないが、確実でないボーナス返済よりも、ボーナスが出たときに繰り上げて返済する繰上げ返済が人気になっている現在では、繰上げ返済手数料もバカにならない負担になる。また、金利タイプを固定から変動、変動から固定と変更する際にも手数料がかかるため、返済プランに繰り上げ返済や金利タイプ変更を見込んでいる方はチェックする必要がある。
繰り上げ返済の手数料には、大きく分けて「一部繰上げ返済手数料」「全額繰上げ返済手数料」があり、ネット銀行などではどちらも無料に設定しているところが多く、都市銀行などでは有料もしくは、「全額繰上げ返済手数料」のみ有料という形が多い。全額返済されると銀行側の収益が下がるので、手数料を高めに設定するという従来の手法である。ちなみに、繰り上げ返済の手数料がかかるところも、だいたい5000円~31,500円程度である。銀行によっては、選択している金利タイプによって手数料が違うところもあるので要チェックだ。また、金利タイプの変更手数料も銀行によって、無料から有料までさまざま。住信sbiネット銀行のように無料の銀行もあれば、ソニー銀行のように「各月の利息差額を現在価値へ還元し、その合計を金利タイプ変更手数料とする」とつまり、金利タイプの変更で得られる返済額の削減メリットは手数料としていただきますよ。といった銀行もある。
5.その他の諸費用
他に諸経費は何が、いくらかかるのか?2012年11月時点での住信sbiネット銀行のケースで確認してみよう。
【借入前】
証明書発行手数料 : 840円
【借入時】
事務手数料 : 借入額の2.1%
印紙税 : 100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
抵当権設定費用 :
登録免許税 抵当権設定額(=借入額)の0.1%~0.4%
司法書士への報酬登記実費 6~10万円程度
【返済時】
一部繰上げ返済手数料 : 変動金利 0円 固定金利 0円
全額繰上げ返済手数料 : 変動金利 0円 固定金利 31,500円
金利タイプ変更手数料 : 変動金利 0円 固定金利 0円
条件変更手数料: 5,250円
住宅借入金等に係る借入金の年末残高証明書 : 0円
住宅借入金等に係る借入金の年末残高証明書(再発行) : 0円
残高証明書 : 840円
利息証明書 : 840円
6.まとめ
まずは、事務手数料が全体の負担額の9割を占めていることがわかる。大手都市銀行の場合は保証料になるため、住宅ローンの比較検討の際は、やはり「保証料」「事務手数料」「団信特約料」の3点を見ながら比較するのが賢い方法である。