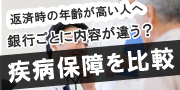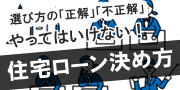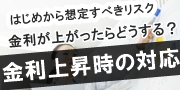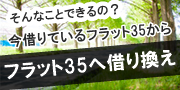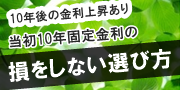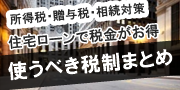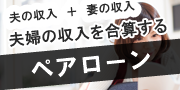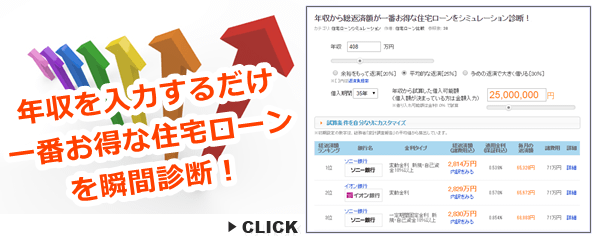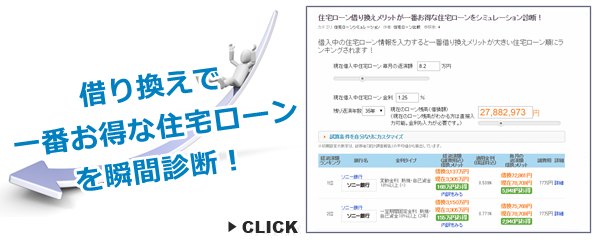住宅購入資金で相続対策が可能?使わなければ損をする!住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: 住宅ローンと税金
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 5247
住宅購入資金で相続対策が可能?使わなければ損をする!住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは
 住宅ローン減税(住宅ローン控除)の陰に隠れて、住宅購入支援の景気対策の一環として「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」というものがあります。今回は住宅ローン減税(住宅ローン控除)と同じくらいにメリットが大きいけれども、いまひとつ知られていない「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について解説します。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の陰に隠れて、住宅購入支援の景気対策の一環として「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」というものがあります。今回は住宅ローン減税(住宅ローン控除)と同じくらいにメリットが大きいけれども、いまひとつ知られていない「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について解説します。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措とは
父母、祖父母から住宅購入に関する資金を贈与してもらった場合に、一定金額を上限として贈与税が非課税(税金0%)になる制度のこと
を言います。
贈与税とは
個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金
のことです。
贈与税の税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
と仮に住宅購入時に2000万円の自己資金を父母から支援してもらったとしたら、基礎控除が110万円なので
(2000万円 - 110万円) × 50% - 250万円 = 695万円
もの贈与税が発生するのです。
仮に住宅購入時の資金を支援してもらわなかった場合は、父母が亡くなられたときに相続税が発生します。
相続税とは
亡くなった人の財産を相続人がでもらうときに 支払わなければならない税金
のことです。
相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
資産が8000万円だとしたら
基礎控除額:3000万円 + 600万円 × 相続人(仮に2人) = 4200万円
残りの3800万円が課税対象
3800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
が相続税ということになります。
本来2000万円贈与していたら発生しなかった税金は税率20%で見ると、400万円の相続税が発生するのです。
相続税が発生する前に住宅購入資金として贈与しておけば、相続税が発生しないことになるので将来的な相続税負担が軽減できることになるのです。
相続税対策として、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は非常に有効な方法と言えます。
「でも、うちの家はそんなに資産がないよ。」
という方も多いかと思いますが、相続税は資産に対して課税されるものです。
仮に東京都内に戸建を持っていただけでも、優に「基礎控除額:3000万円 + 600万円 × 相続人」は超えてしまう可能性が高いのです。
貯金が少なかったとしても、不動産や有価証券、ゴルフ会員権、自動車などの財産があるだけで相続税が発生してしまう可能性は十分にあります。
しかも、この場合には現金を相続しないのに相続税を支払わなくてはならないので、財産を急きょ売却するなど資金繰りを考えなければなりません。
これらのリスクを回避するためにも、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措」を利用して父母や祖父母の財産を次世代に移しておくことが重要なのです。
金額によっては、住宅ローン減税(住宅ローン控除)以上のメリットが出る可能性もあります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措の控除限度額
2016年5月時点
| 住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 住宅を消費税10%で取得 | 住宅を消費税10%以外で取得 | ||
|---|---|---|---|---|
| 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | |
| 平成28年1月~平成28年9月 | - | - | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
| 平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措の概要
2016年5月時点
| 相続時精算課税制度 | 住宅取得等資金の非課税制度 |
|---|---|
| 非課税枠 | 300万円~3000万円 ※別表参考 |
| 併用 | 相続時精算課税制度と併用可能。 |
| 贈与者 | 直系尊属(受贈者の父・母・祖父・祖母等) ※年齢制限なし |
| 受贈者 | 贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属 日本国内に住所を有する人 合計所得額が2,000万円以下 |
| 税率 | 「非課税枠+基礎控除額」を超える部分に対して累進課税(10%~55%) |
| 贈与財産 | 自己の住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること |
| 適用期間 | 平成27年1月1日から平成31年6月30日の贈与 |
| 物件の要件 | ・床面積(登記簿面積)50㎡以上 240㎡以下 ・店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅 |
| 中古住宅購入時の追加要件 | ・耐火建築:家屋の取得の日以前25年以内に建築 ・耐火建築以外:家屋の取得の日以前20年以内に建築 ・一「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結証明」 ・耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合 |
| リフォーム時の要件の追加要件 | ・工事費用が100万円以上であること ・居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。 ・「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明された工事であること |
| 手続き | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用に関する書類を納税地の所轄税務署に提出 |
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措利用の注意点
父母や祖父母からの贈与である必要がある
直系尊属からの住宅取得資金に対して適用される非課税制度です。子や孫の配偶者は対象外になります。
贈与を受けるものは20歳以上
贈与を受ける対象者は贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上である必要があります。
収入が2000万円以下の方
贈与を受ける人は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければ利用できません。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)と同じ住宅要件がある
- 床面積(登記簿面積)50㎡以上 240㎡以下
- 店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅
- 中古住宅の場合は耐火建築であること
- など
です。とくに注意が必要なのは、床面積(登記簿面積)50㎡以上というのは壁の内側を測る内法面積であって、不動産のパンフレットに記載されている壁芯面積ではないということです。パンフレット上で50㎡となっていたら、登記上はそれよりも小さくなってしまい、この非課税制度が受けられない可能性があるのです。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措利用を受けるための手続き
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
- 贈与税の申告書
- 計算明細書
- 戸籍の謄本
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
- 新築や取得の契約書の写し
などの書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
まとめ
親や祖父母の財産が不動産や有価証券を合わせて、3000万円を超えるようであれば相続税が発生する可能性が高くなるため、相続対策としての住宅購入資金の支援を相談してみることをおすすめします。
あくまでも相続税対策として「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措利用」を活用すべきなのです。